はじめに
自治体の予算は、単年度主義といわれ、翌年度以降の支出を内容とする契約は原則として締結できませんが、「長期継続契約」はその例外です。本稿は、この制度がどのような場合に適用となり、類似の制度とどうちがうのかなどをわかりやすく解説する記事です。
予算単年度主義とその例外
自治体の各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって充てることとされています。これらの歳入歳出は、予算として定められますので、これを会計年度独立の原則又は予算単年度主義といいます。
しかし、自治体は、施設の建築工事や道路・橋の建設工事のように1年間では終わらない事業をたくさん行っています。そうした場合には、「継続費」「繰越明許費」「債務負担行為」といったものを予算書に定め、歳入歳出予算と一緒に議会の議決を得て、複数年度の事業を発注し、契約し、執行することとなります。
「長期継続契約」も翌年度以降にわたる契約を締結できるという意味では、その例外の一つです。
なお、「継続費」「繰越明許費」については、別のブログ『会計年度をゆがめる処理―自治体経理の基礎2』をご覧ください。
長期継続契約を締結できる場合
それでは、どのような契約について長期継続契約を締結できるでしょうか。
- ①電気、ガス、水の供給や電気通信役務(電話等)の提供を受ける契約
- ②不動産を借りる契約
- ③その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすような、物品の借入れ又は役務の提供を受ける契約で、条例で定めるもの
上記①と②については、内容が明確ですので、③について説明します。
どのような契約がこれに該当するかというと、「商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの」、「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの」等に係る契約とされています。例えば、OA機器等の借入れ契約や庁舎管理業務委託契約です。
そのほか、車両の借入れ契約や情報処理業務、給食業務、保育業務、廃棄物処理業務の委託契約など自治体によってさまざまな契約を定めています。
なお、③については、条例で定めることが必要です。自治体にその条例がない場合には、長期継続契約の対象とはなりません。
債務負担行為とのちがい
この長期継続契約は、債務負担行為を設定せずに、契約を締結することができます。歳出予算に所要額を計上すれば、個別に債務負担行為としての議決を得る必要はありません。
その反面、債務負担行為を設定すれば、その事業にかかる翌年度以降の支出は義務費扱いになりますが、長期継続契約については、各年度の予算の範囲で給付を受けることとなります。
長期継続契約については、こうしたものができるという規定なので、これに該当するものについて、債務負担行為を設定しても違法の問題は生じないと思われます。
なお、債務負担行為については、別のブログ『「債務負担行為」ってなに?-わかるお役所用語解説25』をご覧ください。
留意点
長期継続契約は、長側の事務処理の効率化の点ではメリットがあります。
一方、契約期間について、あまりに長期間としますと、その間に契約内容を見直すことができなくなり、結果として、「高くつく」ことも考えられます。
そのあたりのバランスをとることが大切です。自治体によっては、年限を規則で定めている団体もあります。
また、条例での対象業務の定め方として、条例本体に個別の業務を列挙せず、例えば、「役務の提供に一定の投資が必要なもの」などの性質を示すだけのもの、あるいは、そうしたうえで、規則で具体的な業務を定めるものなど、自治体によってさまざまなやり方があります。
条例本体に個別業務を定めない場合には、当該業務について、長期継続契約を締結することの適否を一度も議会が判断しないこととなるので、新たな業務を長期継続契約の対象とするような場合には、議会側との意思疎通について注意が必要となることもあるのではないでしょうか。
根拠法令等
本記事の根拠法令等は次の通りです。
解説は分かりやすくするために、主な事項だけを説明したり、法令にはない用語を用いたりしている場合があります。
正確に知りたい場合には、条文や文献等を確認してください。
地方自治法第234条の3(長期継続契約)
同法第208条(会計年度独立の原則)
同法第212条(継続費)
同法第213条(繰越明許費)
同法第214条(債務負担行為)同法第234条の3(長期継続契約)
地方自治法施行令第167条の17(長期継続契約を締結することができる契約)
「地方自治法の一部を改正する法律等の施行について(通知)」(平成16年11月10日付け各都道府県知事あて総務省自治行政局長通知)(長期継続契約の適用範囲の拡大に関するもの)

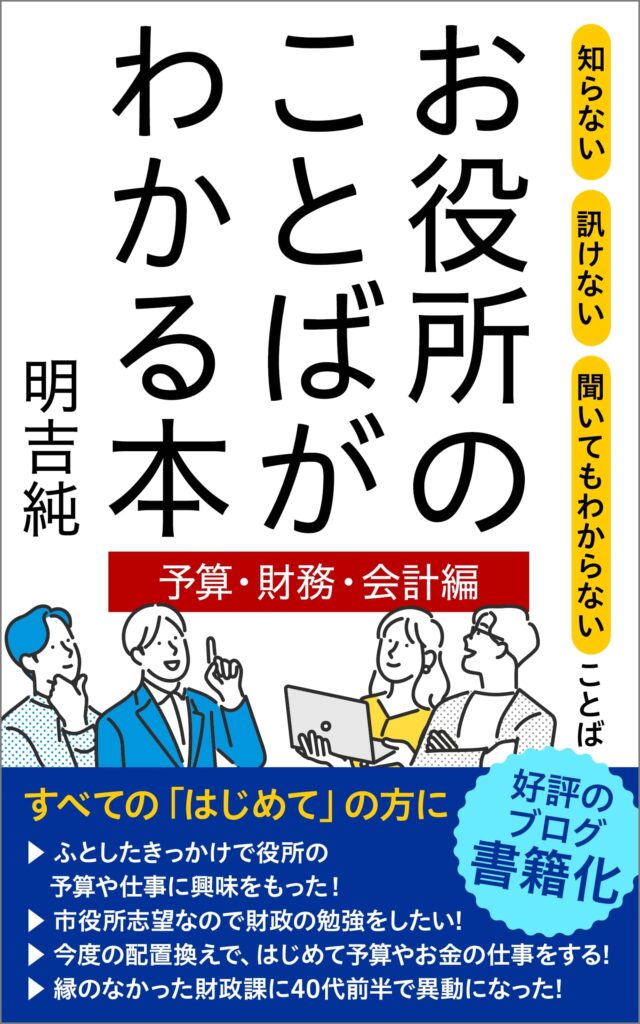

コメント