はじめに
自治体は毎日のように多額の金銭を収入し、支出しています。金銭の取扱いは、厳格に行い、不正を許さないようにしなければなりません。そのため、法律で、支出の方法やそのような支出を行うことができる場合を細かく定めています。
本稿は、自治体の支出の手続についてわかりやすく解説する記事です。
自治体の支出の原則と例外
自治体が金銭を支出する場合には、債権者に対して、(相手の債務の履行が条件の場合には)債務の履行を確認し、自治体の債務の履行時期において、その額(支払額)を確定し、自治体の会計窓口又は指定金融機関において直接、行うことが原則です。
その原則の例外となる支出方法として、「資金前渡」「概算払」「前金払」「繰替払」「隔地払」「口座振替」が定められています。例外といっても、数が少ないということではありません。むしろ、こうした支出方法の方が多く用いられているでしょう。
以下、例外となる支出方法について、説明します。
資金前渡
「しきんぜんと」と読みます。
「資金前渡」とは、自治体の職員に前もって現金を交付することです。その職員は、それにより債権者に対して債務の履行(金銭の支出)をすることになります。
どのような場合に資金前渡ができるかは、地方自治法施行令(以下「施行令」といいます)第161条に規定されています。
この条文には、「外国において支払をする経費」「遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費」「生活扶助費」など16項目が定められています。
それに加え、それらに該当しないものでも、「前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費」で自治体が「規則」で定めるものは、資金前渡ができることとされています。
自治体では、この規定を受け、財務規則などに資金前渡できる費目について、細かく規定しています。内容は、自治体によって様々ですが、いくつか例を挙げると、研修会受講料、講演をした講師に対する謝金、有料道路代、駐車料金、見舞金、切手購入費、自動車重量税のようなものです。
資金前渡を受ける職員の範囲に特段の定めはありませんが、資金前渡に係る現金の交付を受けた者について、財務規則等で、その保管について、銀行預金の方法等によって確実に保管し、支払に当たって原則として領収書を徴し、用務が終わってから精算をするなどの規定が定められていることが一般的です。
概算払
概算払は、自治体が支払う債務額が確定する前に概算で交付し、確定後に精算を行うものです。
概算払ができる場合として、施行令第162条に、「旅費」「官公署に対して支払う経費」「補助金、負担金及び交付金」などが定められています。
それとともに、資金前渡の規定同様「経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費」で自治体が「規則」で定めるものが規定されています。
例えば、補助金などは、補助を受けて事業を行う者にとって、補助対象事業が終わってから補助金を受ける原則を貫くと、その間の資金を別途調達しなければならなくなります。実際問題として、困難である場合も多く、せっかく用意した補助金が使いにくいものとなってしまうおそれがあります。(ただし、概算払の時期が遅いケースもままあります。)
概算払は、冒頭に述べた通り、必ず精算が伴うものです。概算払額と事業終了後の額が同額であっても、必ず額の確定をして、ゼロの精算を行います。
前金払
前金払は、確定している債務について、履行の完了前に自治体が支払うものです。債務が確定している点で、確定していない債務に対して支払う概算払と異なります。
前金払ができる場合として、施行令第163条に、「官公署に対して支払う経費」「補助金、負担金及び交付金」「前金で支払をしなければ契約しがたい請負,買入れ又は借入れに要する経費」などが定められています。
それとともに、資金前渡の規定同様「経費の性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費」で自治体が「規則」で定めるものが規定されています。
施設の建築や土木工事などの請負(いわゆる「公共工事」)については、一定規模のものについては、一定額の前金払を行うことが通常です。こうした工事については、資材の調達にお金がかかりますし、期間を要する工事については、その間の人件費等の負担もあります。円滑な工事の遂行には必要なことです。
前金払は債務が確定していますから、精算の概念はありません。工事完了後には、契約額から前金払の額を控除した残額を支払うこととなります。請負工事では、工事内容の変更や追加などが行われ、それに伴い支払額が変更されることもありますが、それは本項による精算ではなく、契約内容の変更に伴う債務額の変更です。
繰替払
繰替払は、自治体が収納した現金を歳入として整理する前に、経費の支払いに充てる支出方法です。
繰替払ができる場合として、施行令第164条に、地方税の報奨金の支出には当該地方税の収入金を、競輪、競馬等の的中投票券(いわゆる「当たり馬券等」)の払戻金等の支出には、発売した馬券等の発売代金を繰替払できることなどが定められています。
それとともに、「経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費」で自治体が「規則」で定めるものについて、自治体の定める収入金で繰替払できることが規定されています。
具体的に、馬券等の売り上げが千万円あって、当たり馬券の払い戻しが300万円あった場合には、その千万円から300万円を払っていいということです。(当たり馬券用のお金を別途用意しなくてもよいということです。)
注意しなければならないのは、自治体には「総計予算主義」の原則がありますから、会計上の処理としては、歳入額を千万円と、歳出額を300万円とそれぞれの予算科目に整理することです。これを単に差し引き700万円の収入と処理してはいけません。
自治体の財務規則等には、そうした処理をすることが定められています。
なお、総計予算主義については、別のブログ『公務員試験で出題されることがある「予算の原則」とは』をご覧ください。
隔地払
隔地払は、外国や国内ではあるが当該自治体の区域外の隔地又は区域内の隔地にいる債権者に対する支払の方法です。
「隔地」とは、遠い場所や辺ぴな場所をいい、隔地に該当するかどうかは当該自治体が判断します。
隔地払は、会計管理者が支払い場所(金融機関)を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせ、その旨を支払通知書により債権者に通知して行う支払の方法です(施行令第165条)。
なお、指定金融機関等については、別のブログ『「指定金融機関」ってなに?-わかるお役所用語解説28』をご覧ください。
口座振替の方法による支出
債権者が自治体の指定金融機関、指定代理金融機関その他長が定める金融機関に預金口座を設けている場合に、債権者からの申出により、その預金口座に振り替えて支出することです(施行令第165条の2)。自治体からの還付金や交付金の受領などの際に利用されたことがある方も多いと思います。
自治体が指定金融機関を指定している場合にのみできる支出方法です。
根拠法令等
本記事の根拠法令等は次の通りです。
解説は分かりやすくするために、主な事項だけを説明したり、法令にはない用語を用いたりしている場合があります。
正確に知りたい場合には、条文や文献等を確認してください。
地方自治法第232条の5(支出の方法)
地方自治法施行令第161条(資金前渡)
同令第162条(概算払)
同令第163条(前金払)
同令第164条(繰替払)
同令第165条(隔地払)
同令第165条の2(口座振替の方法による支出)

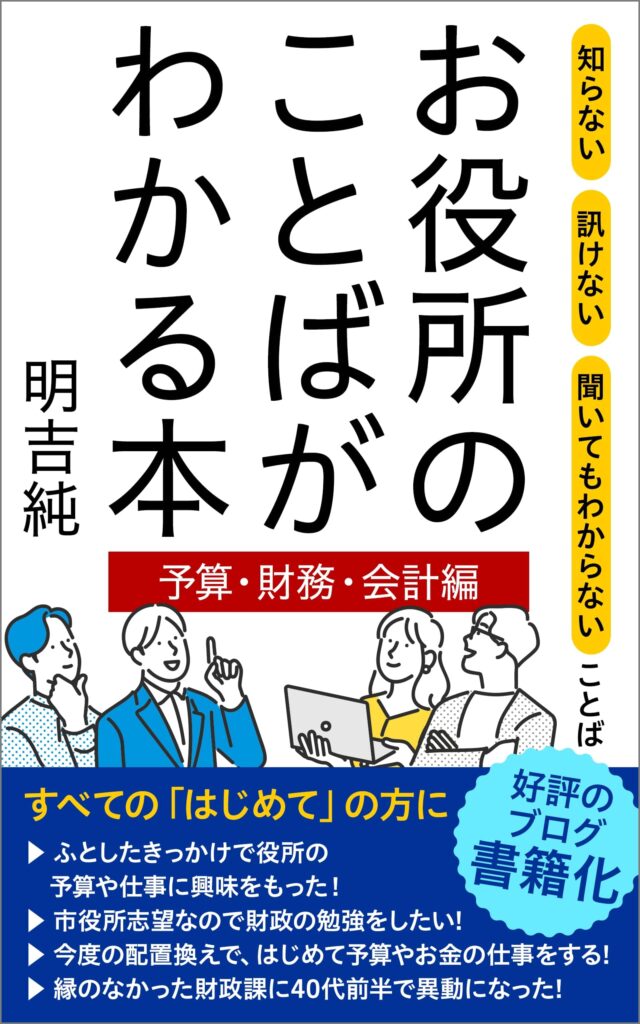


コメント