はじめに
自治体は、毎日、いろいろなお金を収入し、また、支出しています。そのお金は、大別すると、「歳計現金」と「歳入歳出外現金」に分かれます。
本稿は、これらの内容やちがいについてわかりやすく解説する記事です。
自治体の扱うお金(公金)の種類
自治体の扱うお金(公金)としては、まず、予算の歳入歳出に属する現金があります。
自治体の歳入としては、税、地方交付税、使用料・手数料、国庫(県)支出金、地方債などがありますが、これらのお金は毎日のように自治体に入ってきます。また、自治体は、福祉、施設建設やインフラ整備、産業の振興、教育など様々な分野に歳出予算を振り分け、たくさんの事業を行い、支出をしています。
こうしたお金を「歳計現金」といいます。
しかし、自治体は、予算に計上されたお金だけを扱っているわけではありません。例えば、自治体の所有に属さない、入札保証金・契約保証金、公営住宅の敷金や職員等に支払う給与に係る源泉所得税・住民税などは、予算に計上しないものですが、一時的に自治体が預かることになります。
こうしたお金を「歳入歳出外現金」といいます。
そのほかに、自治体では、財産の一種として「基金」を有しており、その基金を構成するものとしての現金を保有しています。基金については、別のブログ『「基金」ってなに?-わかるお役所用語解説4』をご覧ください。
また、収支に一時的な不足を生じる場合に「一時借入金」の借入れを実施する場合があります。一時借入金については、別のブログ『「一時借入金」ってなに?-わかるお役所用語解説24』をご覧ください。
以上、「歳計現金」「歳入歳出外現金」「基金に属する現金」「一時借入金」が一般に「公金」に分類されるものです。
自治体はお金をどこに保管している?
歳計現金については、指定金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管することとされています。
ただし、窓口でお金のやり取りを行う職場がありますが、そのような部署では、一定の現金をカギのかかる金庫などに保管している場合があります。
歳入歳出外現金については、歳計現金の出納、保管の例によることとされており、基金についても同様です。
一時借入金は、その性質上、歳計現金と同じように扱われます。
なお、指定金融機関については、別のブログ『「指定金融機関」ってなに?-わかるお役所用語解説28』をご覧ください。
規定の意味
歳入歳出外現金の出納、保管も歳計現金と同じように扱うということですと、歳入歳出外現金について、歳計現金とは別に定めた意味はどこにあるのでしょうか。
それは、
① 歳入歳出外現金は、法律又は政令の規定によらなければ保管することができない。
② 歳入歳出外現金には、法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか利子を付さない。
ことを明示したことです。
特に、①について、例えば、市の職員が不始末を起こしたので、その職員からの申出により受領したお詫びの金や取引事業者からの十分な債務の履行ができなかったことを理由とした、申出による任意の賠償金などは保管できません。これらについては、自治体がきちんと債権化して請求することが必要です。
自治体はむやみやたらに根拠のない金銭を受け取ることはできないということです。
任意団体に係るお金
自治体が扱う「公金」としては上記の4種類ですが、自治体職員が扱うお金はこれに限りません。例えば、課の親睦団体の運営や業務上関係のある任意団体(〇〇協議会、○○実行委員会など)の経理を課の庶務担当者や業務担当者が行うことは珍しくありません。
これらについては、一般にその団体の規約で収入支出の手続、監査する者や監査の方法が定められています。しかし、そうした定めに関わらず、一者に任せきりにした結果、その者が、団体の資金を私的に流用するケースも散見されます。
公金であってもこうしたお金であっても、不正を行った者は、刑事罰や懲戒処分を受けるおそれがあり、また、損害の賠償も求められるでしょう。
業務上取り扱うお金については、細心の注意をもって、きちんとした事務処理を心掛けることが大切です。
根拠法令等
本記事の根拠法令等は次の通りです。
解説は分かりやすくするために、主な事項だけを説明したり、法令にはない用語を用いたりしている場合があります。
正確に知りたい場合には、条文や文献等を確認してください。
地方自治法第235条の4(現金及び有価証券の保管)
同法第241条第7項(基金の管理)
同法第243条の2の8(職員の賠償責任)
地方自治法施行令第168条の6(歳計現金の保管)
同令第168条の7(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
地方自治法施行規則第12条の5(保管できる現金又は有価証券)

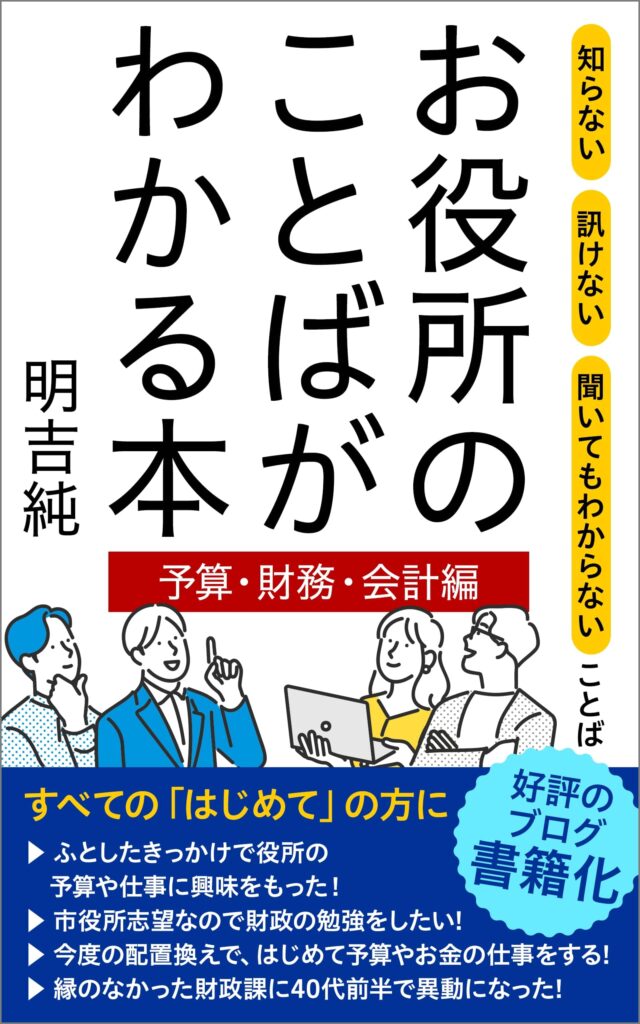

コメント